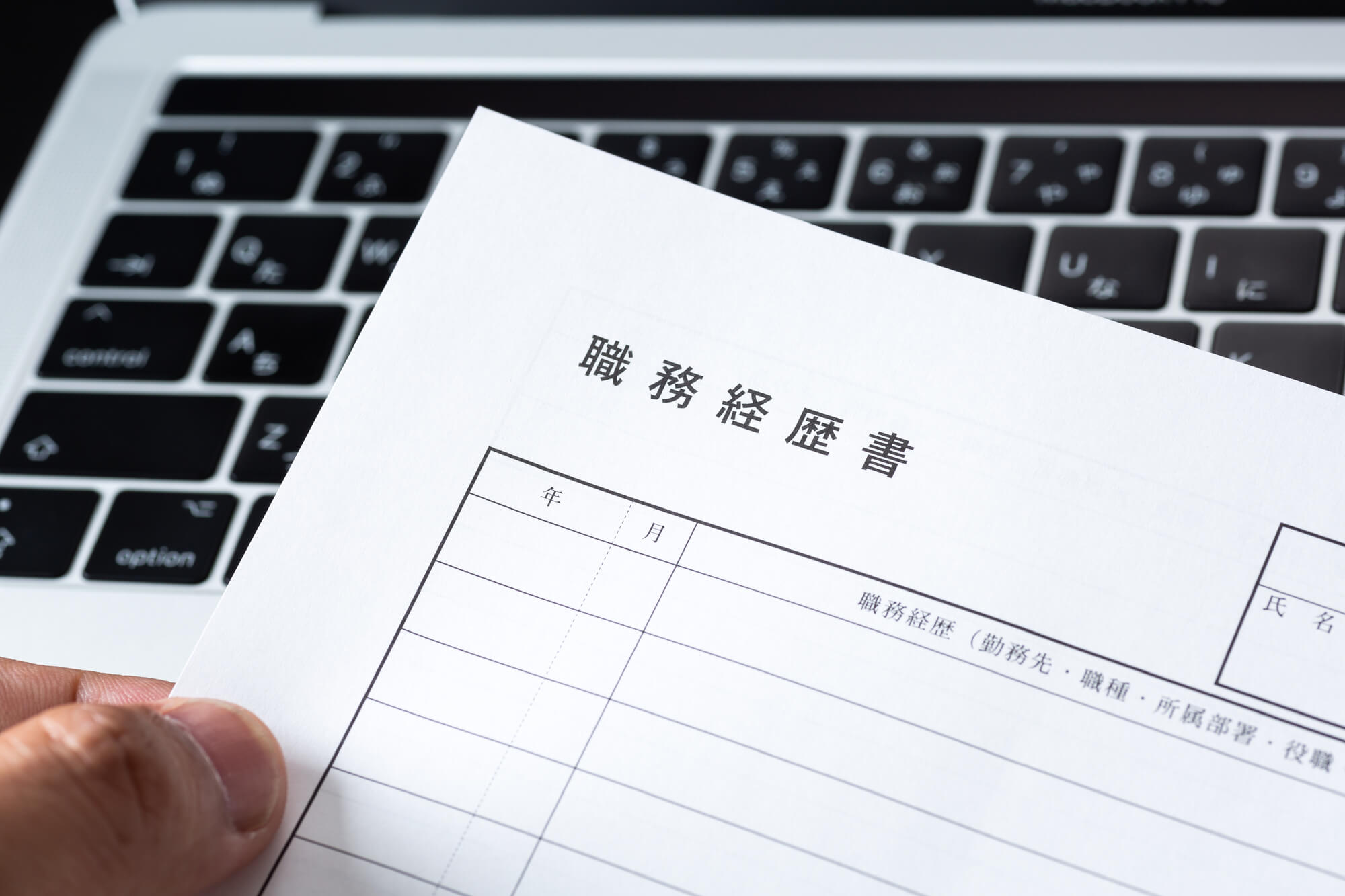「経理はやめとけ」という意見を見聞きして、経理職への転職を迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
どのような仕事にも、メリット・デメリットや向き・不向きがありますが、経理職の実態はどうなのでしょうか。
この記事では、「経理はやめとけ」と言われる理由を整理するとともに、経理としてキャリアを重ねていくためのヒントについても解説します。
経理への転職を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
経理職の実態とは?

会社のお金を管理する重要な役割を担う経理職ですが、その実態はどのようなものでしょうか。
ここでは、経理の日常業務から直面する問題、労働環境まで、経理職の実情について詳しく解説します。
経理業務の基本的な内容
経理の仕事は、会社のお金の流れを正確に記録し管理することです。
経理業務は主に「日次業務」「月次業務」「年次業務」の3つに分けられます。
日次業務では請求書の発行や支払処理、経費精算、会計ソフトへの入力作業などを行います。
月次業務には月次決算や売掛金・買掛金の管理、給与計算などがあり、毎月の締め作業が中心です。
年次業務は年間の業績をまとめる重要な仕事で、決算書の作成や税金の計算・申告、監査対応などを行います。
経理職で直面する一般的な問題
経理職では、期限に追われながら正確さを求められるという二重のプレッシャーがかかります。
特に決算期や税金の申告期限が近づくと、業務量が急増し、ミスが許されない状況で働かなければなりません。
日頃から高い集中力を保ち、スケジュール管理をしながら業務をこなしていく必要があるでしょう。
また、税法の改正や会計システムの変更なども頻繁に起こるので、自発的に勉強を継続することも大切です。
経理は専門性が高い仕事なので、常に新しい知識を吸収していく姿勢が求められます。
長時間労働とその影響
決算期には残業が増えることが一般的で、特に年度末の決算時期は夜遅くまで働くことも珍しくありません。
長時間労働が続くと、体調不良やメンタルヘルスの問題につながるリスクもあります。
特に人員が限られている中小企業などでは、決算期の負担が一人に集中しやすく、体力的にも精神的にも負担が大きくなってしまうことがあります。
ただし、特定の忙しい時期は事前に分かっているので、通常期にはしっかり休暇を取ることも可能です。
経理業務の煩雑さ
経理は、決算までの細かい作業を日々積み重ねていく煩雑な業務です。
毎日の取引を正確に記録したり、数字を何度もチェックしたりする地道な作業が多く含まれています。
また、基本となる「仕訳」一つをとっても、企業によってやり方が大きく異なることがあり、簿記の知識をそのまま使えないケースも少なくありません。
そのため、最初は覚えることが膨大にあり、難しく感じることもあるでしょう。
さらに、他部署や取引先からの突発的な問い合わせに対応する必要もあり、マルチタスクの能力も求められます。
上司や部署間の圧力
経理部門は他の部署からの要望や圧力にさらされることがあります。
営業部門から規則外の経費精算を依頼されたり、経営層から急に数字の分析を要求されたり…
時には「お金の番人」として、無理な支出を断らなければならないこともあります。
また、決算のスケジュールに間に合わせるため、他部署に提出物の催促をしなければならないことも。
経営陣からは厳しい期限を設定されたり、他部署からは「融通が利かない」と思われたりすることもあり、肩身の狭い思いをすることも少なくありません。
経理の仕事の日常的な課題
経理部門の日常には、特有の課題やプレッシャーが潜んでいます。
特に以下の2つは、経理職が日常的に向き合わなければならない大きな課題です。
期末期首の過重労働
月末月初や四半期末、年度末などの決算期は、経理部門にとって最も忙しい時期です。
この時期には膨大な業務をこなす必要があり、残業も増える傾向にあります。
特に上場企業では、決算発表までの期限が厳しく設定されているので、プレッシャーも大きくなるでしょう。
また、決算業務は経理部門だけでは完結せず、他部署からの資料提出や確認作業も必要となるので、他部署への働きかけも重要です。
迅速かつ正確に業務を進めるために、日頃からのシステム整備や業務の効率化、部署間の連携が求められます。
小さなミスが重大な影響を及ぼす可能性も
経理の仕事では、小さなミスが大きな問題につながることがあります。
例えば、1つの入力ミスが決算書の誤りにつながり、会社の信用問題に発展してしまう恐れも。
また、税金の計算ミスが後から発覚すると、追徴課税などのペナルティを受けることもあります。
このような責任の重さから、経理担当者は常に緊張感を持って業務に取り組む必要があるのです。
ダブルチェックやシステムによる自動検証など、ミスを防ぐための仕組みづくりも経理部門の重要な仕事だといえるでしょう。
「経理はやめとけ」と言われる5つの理由

なぜ「経理はやめとか」と言われてしまうことがあるのか、その理由を5つ紹介します。
AIによる代替の可能性がある
近年のAIやRPAの進歩により、経理業務の一部が自動化される可能性が指摘されています。
確かに、データ入力や単純な集計作業といった定型的な業務はAIによって代替可能かもしれません。
しかし、最終的なチェックや判断、イレギュラーな処理は人間にしかできないので、経理の仕事が完全になくなるとは考えにくいでしょう。
むしろ、AIを積極的に活用し、効率的に業務を進められる人材へのニーズが高まっていくのではないかと予想されます。
評価を受けにくい環境
経理は、営業のように目に見える成果を出しにくい部門です。
正確に業務をこなしても「ミスがなくて当たり前」と思われがちで、目立った功績としてアピールしにくい側面があります。
また、経理部門の業績は、どうしても会社の利益に直結していないと見なされがちで、昇給や昇進の機会が限られている企業もあるでしょう。
そうなると業務へのモチベーションも低下してしまうので、転職の際は企業の評価制度などを事前に調べておくことが大切です。
繰り返しの作業に飽きやすい
経理業務には、伝票処理や請求書発行など、定型的な作業が多く含まれるので、こうした繰り返しの作業に飽きを感じてしまう人もいるかもしれません。
近年では会計ソフトの進化により、単純作業は減少傾向にありますが、それでも定型業務が比較的多いのが経理の仕事です。
特に2〜3年経験を積むと、業務に慣れすぎて新鮮味を感じなくなってしまう可能性も。
ただし、定型的な作業が好きな人にとっては、この点が魅力に感じられることもあります。
充実感を得にくい
経理は裏方の仕事なので、直接的な達成感を得にくいと感じる方もいるでしょう。
例えば、頑張って税務調査や監査をスムーズに終えても、その成果はなかなか目に見えません。
また、経理部門の成果は「問題がなかった」という消極的な評価になりがちです。
エラーや不正を防ぐことが主な業務となるため、問題が起きなければ特に評価されず、何か問題が起きれば責任を問われるという難しい立場に置かれることもあります。
それでも、経営者の視点で会社全体の状況を把握できる経理ならではの醍醐味もあるので、自分の価値観に合った働き方を見つけることが大切です。
昇進の機会が限られている
経理部門は組織内でも人数が少なく、昇進のポストも限られていることが多いでしょう。
また、経理専門のキャリアパスが明確でない会社も多く、特に中小企業では、経理部長以上のポジションがないケースも。
さらに、専門職である経理は、同じ部署内でキャリアを続けることが多いので、他部署への異動によるキャリアアップの機会も限られることがあります。
転職の際には、CFO(最高財務責任者)や経営企画など、財務知識を活かした別のキャリアパスも視野に入れておくといいでしょう。
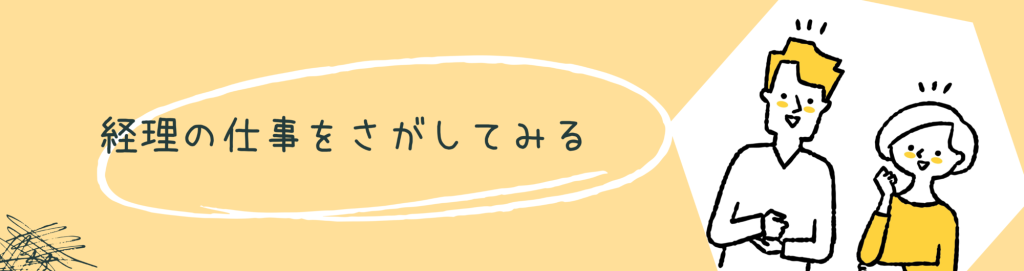
転職前に把握すべき経理のリアル

経理職への転職を考える前に、実際の現場ではどのような状況が待ち受けているのかを知っておくことも重要です。
ここでは、転職前に把握しておくべきポイントをご紹介します。
経理業務におけるストレスの実態
経理業務で最も大きなストレス要因は、締め切りに追われる環境です。
特に月次決算や年次決算には絶対的な期限があり、その中で正確な作業を求められます。
また、金額が1円でもズレていると、後々大きな問題に発展するリスクがあるので、常に緊張感を持って作業する必要があります。
こうした状況から強いプレッシャーがかかり、残業の続く繁忙期には体調を崩してしまうこともあるでしょう。
転職前には、自分のストレス耐性を分析し、作業の効率化やタイムマネジメントのスキルを身につけておくと効果的です。
職場の環境と文化
経理は少人数で運営されていることが多いので、人間関係が仕事の満足度に大きく影響する職種です。
経理職を検討する際は、その会社の経理部門の環境や文化を事前に調査することをおすすめします。
実際の雰囲気や働き方を知る方法としては、インターンシップやOBOG訪問などが挙げられます。
こうした機会を活用して、部署内のコミュニケーションスタイルや、チームの雰囲気、他部署との関わり方などをチェックしておきましょう。
残業時間や繁忙期の過ごし方、会計システムの導入状況や業務効率化への取り組みなども確認したいポイントです。
職業満足度とキャリア発展
経理の専門性を活かして働くためには、長期的なキャリアビジョンを持つことが大切です。
入社前に将来の可能性を見極めておくことが、満足度の高い転職につながるでしょう。
経理職の満足度は会社によって大きく異なるので、「OpenWork」や「転職会議」などの口コミサイトを活用して、実際に働いている人の声を参考にするのもおすすめです。
経理からどのようなポジションに進むことができるのか、スキルアップのためのサポート体制があるのかなども、経理職として働く環境を判断する重要な材料となります。
経理職を長く続けるためのヒント

「経理はやめとけ」という声がある一方で、経理職で充実したキャリアを築いている人も多くいます。
やりがいを感じながら働き、経理の仕事を長く続けるためのポイントをご紹介します。
キャリアアップと専門性の強化
経理職で長く活躍するためには、継続的なスキルアップが不可欠です。
日商簿記・FASS検定といった資格の取得や、会計ソフトの操作スキル向上に加え、税務や財務分析など、特定の分野での専門性を高めるのもいいでしょう。
単なる数字の処理だけでなく、経営に役立つ情報を提供できる「ビジネスパートナー」としての役割を目指すことで、長期的な価値を高めることができます。
会社の研修制度を積極的に活用したり、業界セミナーに参加したりして、常に最新の知識を取り入れることを心がけましょう。
メンターシップの活用
経理業務には、教科書だけでは学べない実務上の判断やノウハウが多く存在します。
そのため、経験豊富な上司や先輩から積極的に学ぶ姿勢が重要です。
また、経理の仕事は一人で黙々と進めることも多いですが、孤立せずに周囲との関係を大切にすることで、モチベーションを保ちやすくなります。
社内のメンターシップを活用し、信頼できる上司や先輩との関係を構築するようにしましょう。
社外の勉強会に参加したり、オンラインコミュニティに所属したりすることも、知見を広げる良い機会となります。
転職とキャリアチェンジの検討
経理のスキルや経験は、様々な場面で活かすことができます。
もしも異なる環境でキャリアを広げていきたいと感じた場合は、転職を検討してみるのもおすすめです。
また、経理経験者は転職市場においても需要が高い人材なので、自分に合った環境を探すことができるでしょう。
経理という軸を持ちながらも、常に自分のキャリアを客観的に見つめ、必要に応じて転職やキャリアチェンジを検討する柔軟さを持つことが、長く働き続けるためのポイントです。
まとめ 未経験の経理転職ならとんがりコラボ
経理業務特有の大変さから「経理はやめとけ」と言われることもありますが、そのデメリットは捉え方によっては魅力にもなり得ます。
経理は企業にとって必要不可欠な機能であり、専門性を身につければ安定したキャリアを築きやすいポジションだといえるでしょう。
経理への転職を成功させるためには、経理職の求人が豊富な転職エージェントを利用するのがおすすめです。
とんがりコラボは、未経験からの経理転職に特化した転職エージェントです。
経理職に精通したアドバイザーが長期的なキャリア形成を考え、「サポートから、面接対策・内定」まで伴走します。
定期的な無料オフラインセミナーやYouTubeチャンネルもありますので、是非ご活用ください。